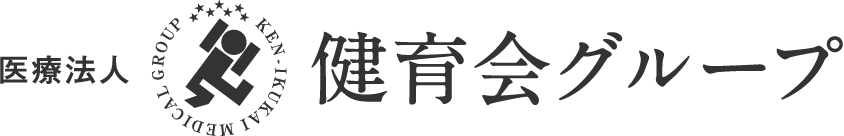今回特別講演の座長は、長年に渡り北海道大学病院リハビリテーション科教授をお務めになり、4月より健育会グループの喬成会副理事長に就任いただいた生駒一憲先生が務めました。

東北大学大学院医学研究科 内部障害学分野 教授 海老原覚先生による特別講演の演題は、「リハビリテーション医療における医師の役割」。今後国内のリハビリテーション界を牽引される気鋭の先生による講演は、大変示唆に富む内容でした。


まず、海老原先生は近年の身体障害者手帳の発行件数のデータから、内部障害者が今後急速に増加することを予測され、「これからは重複障害の時代であり、リハビリニーズもより複雑化・複合化する」という前提を提示されました。そのうえで、脳卒中リハビリを例に、「女性」「高血圧」「認知機能の低下」「インスリン投与」「タンパク尿」「喫煙」などの疾患の発症要因が、機能回復の阻害要因にもなることを明示され、リハビリ科が「機能障害の回復訓練⇒能力障害への代償機能の提供⇒社会的不利益を生まないための福祉資源の活用」に対応すべきだとされました。その際、重要となるのが多職種連携であり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士はもちろん、看護師・薬剤師・歯科チーム・管理栄養士・認知症ケアチーム、さらにはベッドやマットなど周辺環境を整える福祉用具スタッフまで含めたチーム全体を医師が束ねていくことの重要性を指摘。その事例として、前職の東邦大学医療センター時代につくられた嚥下対策チームや石巻健育会病院での活動などをご紹介いただきました。