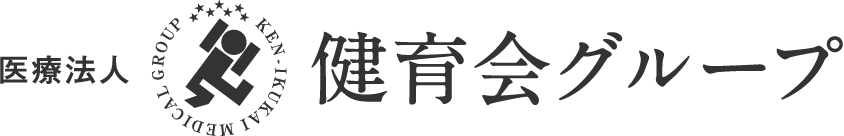今回の予算ヒアリングは非常にレベルが高く、湘南慶育病院の意欲が強く感じられました。今後の課題としては、医師の「愛情を持って親身な対応」の部分が鍵になってくると感じます。
「患者さんに信頼される」ためには、医師が患者さんの顔をしっかりと見て、触れることが大切です。患者さんは医師に触れてもらうだけで安心感を抱きます。
電子カルテの普及やコロナ禍を経て、患者さんとの直接的なコミュニケーションが希薄になっているように感じられます。
患者さんが最期を迎える際には、医師が最後まで付き添い、寄り添う姿勢を見せる。このような取り組みが親身な対応につながっていきます。
実現することは容易ではないかもしれません。しかし、医師をはじめ、全職員が親身な対応を実践することができれば、健育会グループは日本で他に類を見ない医療グループになると確信しています。
手術支援ロボット「ダビンチ」の導入による影響については「自分たちでどのように貢献するか」「ダビンチをいかに活用するか」といった、皆さんの積極的な姿勢が強く伝わってきました。
ヒアリングでは「ダビンチ」導入によって赤字が生じるという報告がありました。しかし私は、この先行投資はいずれ必ず利益を生み出すと確信しました。
赤字という結果をマイナスと捉えず「ダビンチ」を積極的に取り入れてください。
最先端の医療機器を導入することは、これまで見えていなかったものが認識できるようになり、診察の速度を上げ、手術件数の増加につながります。
健育会グループ全体は投資する余裕もあるので、有益と思われる技術や機器については積極的に導入を進めていきましょう。
職員の負担軽減や業務の効率化につながるのであれば、導入を検討する価値があります。
一方で、不必要なものの導入は見送るべきです。経営において、その必要性をしっかりと見極めてください。
必要であると強く感じているものについては、遠慮せずにマネージングディレクターに相談してください。価値ある投資は、将来的に実を結ぶと信じています。

かつて藤沢市は市民に対し、病院建設の構想を語っていました。一方、慶應義塾大学SFC研究所の学部長は、SFCの有効な政策を導き出すことについて考えていました。
そのような折、相鉄本線の湘南台延伸計画が発表され、病院建設の動きが活発化し、慶應義塾大学SFC研究所から健育会グループに設立の話が持ち込まれました。
「健康と文化の森地区」に位置する湘南慶育病院は、神奈川県と藤沢市の期待に応えるべく誕生したのです。
県は慢性期医療を、市は急性期医療の提供を望んでおり、私たちは救急医療の病床数を調整するなどして日々、病院の発展に努めています。
県と市の双方の要望に応えることは、私たちの使命です。
これまで通り、質の高い慢性期医療の提供と、最先端の医療を実施していけば「全ての方にとって理想的な病院」に成長することも叶うはずです。
県と市の期待を背負っているという使命を胸に、引き続き頑張っていきたいと思います。