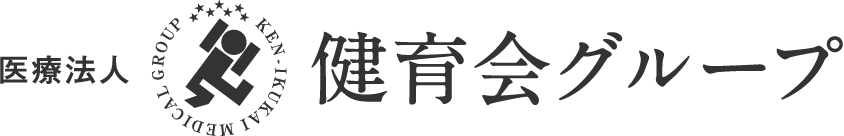まず、健育会グループが掲げる「MVV」の「ミッション」についてお話しします。組織の存在意義についてのお話です。
先代から病院を継ぐという話が出た頃、私は研究者になることも、病院で診察に当たることも興味があるような立場でした。私は「病院を経営する意義が果たしてあるのか」ということを考え、世の中になくてはならない組織となるためにはどうすれば良いのかを明確にし、「光り輝く民間病院グループ」を使命に掲げました。
私が理事長に就任した当時は、民間医療は質の悪い経営を行っている、といった悪い風潮がありました。しかし、その一方で公立病院は常に赤字経営でした。一定のレベルの医療を行えば赤字になる、ということが当たり前の時代です。そこで私は、医療従事者としては初めて公益社団法人経済同友会への入会を決め、医療改革委員会の委員長に就任し、「民間医療だからこそ成せる強さ」の実例を出すことに力を入れました。
そのうちの一つである「海外からの医療従事者の受け入れ」は、大きく評価を受け、2013年9月には、当時の天皇皇后両陛下による行幸啓訪問にケアポート板橋をお選びいただきました。

政府は病院の民営化を推進してはいるものの、民間医療の効率化はまだまだ浸透していません。
今もなお、医療費の抑制政策が続いており、病院の4分の3は赤字経営が続いていると言われています。しかし、見方を変えれば、4分の1の病院は黒字経営ができているということになります。私は、マネジメントにおいても力のある、黒字経営を行える病院が日本の医療を支えてくべきだと考えています。
今年の7月に日本経済新聞のコラム『Deep Insight』に、健育会グループの取り組みが掲載されました。私が理事長に就任した当初から取り入れていた医経分離の「ツートップ制」を筆頭に、健育会グループは工夫次第で効率的で質の高い医療を提供してきた、と述べられています。工夫を凝らすことで危機を打開できることこそが民間のなせる技であり、私はその姿勢を今もなお追い求めています。
介護においては、「活力のある高齢社会のサステナビリティを実現する」ことを掲げています。日本の出生率が低下していく中、高齢化社会になることは止められません。私はこのような状況の中で、いかに活力を生み出せるかが介護事業に必要だと考えました。高齢化社会が進むことで今後、高齢者は孤独死や、満足にサービスを受けられない状態で誰にも看取られずに亡くなる人々が増大するとされています。私は、このような人たちを決して出してはいけないと強く思い、介護事業に力を入れました。また、現役で働いている世代が、介護によって仕事ができなくなることにも問題を感じています。介護はプロに任せ、働くべき人たちが仕事に没頭できるような社会を作らなくてはなりません。
医療と比べ、介護事業は民営化が広がり、急速に拡大しています。その背景には「スピード」と「チャレンジ精神」が根底にあります。
では、公立の医療・介護と、民間とでは何が違うのか、具体的な例を挙げながら説明していきたいと思います。