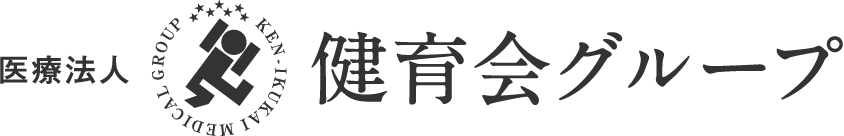今から13年前、東日本大震災で石巻港湾病院(現:石巻健育会病院)が津波被害を受けました。海沿いに近い病院のため、地震が発生する以前から、氾濫したケースを想定した訓練をいつも行っていましたが、その想定以上の津波が襲ってきました。悲しいことに、訪問看護に出ていた職員と、病院のことを心配して自宅から駆けつけようとした職員の方3名が津波に巻き込まれて亡くなりました。しかし、病院の中にいた患者さん、職員は誰一人として被害に遭いませんでした。
直接的な被害はなかったものの、市は食料を分けることすらまともに行ってくれませんでした。3月の極寒の中、職員たちは自分たちが着ている服を患者さんにかけて励ましました。ライフラインが断絶した状況の中で過ごすうちに、職員は「このまま患者さんと私たちは凍死するのではないか」と思ったそうです。36時間後、道路事情が落ち着き、本部から救援に向かった部隊と連絡が取れ、最低限の資材物資を届けることができました。これらの支援活動は、全てボランティアとして職員たちが自ら率先して行ったことです。
その後、石巻港湾病院は瞬く間に復旧をしました。ガスが開通していない状態の中、健育会グループのネットワークを通じ、グループ全体でサポートを行いながら対応し、わずか半年で元の医療状態に戻しました。
健育会グループのスピーディーな行動に対し、石巻市立病院の取った行動は、病院閉鎖でした。国からの援助がありながらも石巻市立病院は、自衛隊を駆使して全ての患者さんを被害のない病院へ搬送し、医師や看護師たちは歩いて誰もいなくなった病院を後にし、早々に復旧を断念したのです。
健育会グループは、グループの支援によってわずか半年で完全復旧をしました。それに比べ、石巻市立病院は病院閉鎖の道をたどりました。私はこの対処の差、スピードの差こそ、典型的な民間病院と公立病院の差だと思っています。健育会グループと石巻市立病院の復旧における力の差は、医療雑誌『医療タイムス』にも取り上げられました。
東日本大震災による被害からの復旧に関して、いわき湯本病院の例もご紹介します。いわき湯本病院は、内陸に位置していたため、津波の被害はありませんでした。震災直後は給水車が来ていましたが、地域に住んでいる人々は風評被害による二次災害を受け、次々と街を去っていきました。人口が減り、ガソリンもなくなってしまったことで、市は給水車による配給を停止し、いわき湯本病院は水のライフラインが途絶えてしまいました。
そこで健育会グループは、本部のネットワークを駆使し、静岡から給水トラックを手配して水を配送しました。全てのライフラインがつながり、いわき湯本病院は、病院の機能を継続することができました。
次に、西伊豆健育会病院の例を挙げます。西伊豆地区には当時、救急病棟が存在しませんでした。そのため、患者さんを病院に搬送する間に、出血多量で亡くなってしまった、というケースが起こり、街や県の人々から救急病院を作ってほしいという要請が上がりました。私は、医療というものは「地域から求められていることに応える」ことこそ使命であると感じているため、すぐにその要請を受け入れました。救急医療の現場では、万が一の事態が起きた際の責任の所在を懸念し、手を引く病院も存在します。健育会グループでは理事長である私が全責任を負う、と言っているため、西伊豆健育会病院では「絶対に救急搬送を断らない」という理念を今もなお持ち続け、救急医療により集中して活動を行っています。
コロナ禍における対応についてもお話しします。当時、2,000の病床を抱えながらも、健育会グループには、新型コロナウイルスの専門病院が一つもありませんでした。私は社会貢献のために早急に石川島記念病院をコロナ病院にするという判断を下したところ、この対応を職員はすぐに受け入れてくれました。それまで救急も行っていなかったリハビリ病院でしたので、コロナ患者を受け入れるためのシミュレーションを行い、リハビリ患者用だった47床を18床に減らしてコロナ病床にあてました。当時の状況は『報道ステーション』にも大きく取り上げられました。