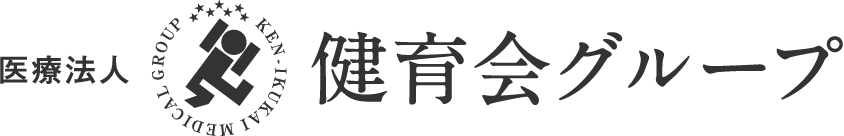公益財団法人 日本尊厳死協会の北村義浩理事長と、本人の意思が尊重され、苦しむことなく最期を迎えることができる治療のあり方について対談しました。
日頃から、私は延命措置のあり方について悩みを抱えていました。
先日の会議で院長から、鼻からの経管栄養チューブを何度も自己抜去してしまい、その都度挿入するのは患者さんがつらい思いをすると思うが、身体抑制はしない方針なのでそのジレンマで悩んでいるとの報告を受けました。私は、本人がそれほどまでに嫌だと感じているのであれば、その意思を尊重してチューブを抜去すれば良いのではないかと提案しました。
しかし、私の提案に対して、その場にいた医師たちは皆口をつぐみ、議論は深まらず、議題は終わってしまいました。
延命措置のあり方について深い疑問を抱える中、朝日新聞の「オピニオン&フォーラム」に掲載された、療養型病院で働く医師のコラムに大きな共感を覚えました。
※末尾の参考資料1参照
そのコラムには、担当患者の大半が鼻からの経管栄養または胃ろうで栄養を摂取し、さらに身体抑制具であるミトンを装着して延命措置を受けているという、日本の終末期医療の実態が記されていました。この状況に対し、執筆した医師は「果たして患者本人の意思が尊重されているのか」という強い疑問を呈していました。私は、自身が抱える悩みと同じ問題意識を持つ医療従事者が数多くいることを痛感し、改めて延命措置の是非についてより深く考えなくてはならないと感じました。
回復の見込みがない「出口のない延命措置」は、患者さん本人だけでなく、ご家族、そして医療従事者、誰もが苦しみを抱え込んでいます。
そこで、回復の見込みのない終末期において、延命措置を望まない人の意思を尊重する社会づくりを目指して活動されている、公益財団法人 日本尊厳死協会の理事長を務める北村義浩先生に、患者さんが穏やかに最期を迎えるためには、具体的にどのような体制が求められるのか、お話を伺いました。