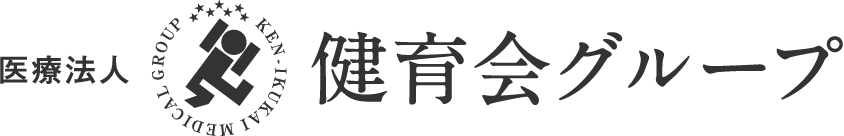北村先生健育会グループでも、延命措置の判断に困るケースはよくありますか。
竹川理事長非常に多くあります。健育会グループでは原則として身体抑制を行っておりませんので、患者さんが経管栄養のチューブを自己抜去してしまうケースが頻繁に見受けられます。私は、患者さんの行動に対し、ご本人がそれほど苦痛を感じているのであれば、チューブを入れなくても良いのではないか、と考えています。
北村先生その措置は、法律的には何の問題もありません。明確に言えば、「良い」と定めている法律もなければ、「良くない」と定めている法律もないのが現状です。しかし、問題は、ご家族から「どうして延命措置をしてくれなかったのか」と訴えられる民事的なリスクが生じるという点にあります。
竹川理事長延命措置を行う段階では、本人の意思疎通が図れない状態であるため、指針が定まらないという部分が難しいですね。たとえ患者さんの尊厳を守るためと思って措置を中止しても、ご家族に「あの病院は必要な処置をしてくれなかった」と思われてしまう可能性があります。「出口のない延命措置」は、患者さん本人も苦痛を伴い続けますし、医療費がかかりご家族も辛く、誰も喜ばない状態です。だからこそ、本来は国がガイドラインを作るべきだと考えます。
北村先生実は、2018年に厚生労働省が、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という、人生の最終段階における意思決定を、「人生会議」という愛称に決定し、その普及啓発を推進しています。日本尊厳死協会では、人生の最終段階を穏やかに迎えるために、事前にご本人の治療に関する要望を記載した指示書のもと、医療・ケアチームやアドバイザーなどから十分な説明を受け、ご家族を含めた話し合いを繰り返し、より良い選択をすることを推奨しています。
ご本人がしっかりと意識を持っている状態で延命措置について事前に言及してくれていれば、その後、誰もが納得した処置を行うことができます。