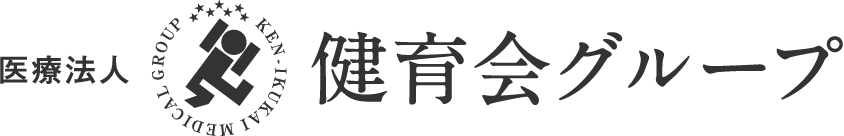竹川理事長そのような問題は、病院で対処するものではなく、法律の世界の話になりますよね。きちんとした記録を武器にし、あとは法律のプロフェッショナルである弁護士に任せるべきです。ですから、民事訴訟を恐れて、患者さんの穏やかな死を手助けすることをためらうようなことはあってはならないと思います。
北村先生いざ決断を迫られた瞬間には、「はい、わかりました」としっかり明言されますし、サインもするのです。ですが、後になって「そんなことは思っていなかった。無理矢理サインさせられた」などと言われ、ショックを感じることもあります。
竹川理事長やはり、まずはご家族から信頼を得ることが大事になってきますね。「お父さん、今苦しいと思いますよ」などと看護師が優しく語りかけてみたりする。ご家族の気持ちや意見にきちんと耳を傾け、信頼し合う関係ができていることが重要です。「この病院は真剣にうちの親族のことを考えてくれるんだ」と思ってもらえていないと、委員会を発足したとしても受け入れてはくれないでしょう。
北村先生患者さん、ご家族、医療従事者の話し合いを通じて、患者さんの価値観を明らかにし、これからの治療・ケアの目標や選好を明確にするプロセスは、主治医、看護師、ご家族、ご本人と、最も少ない場合で4人で行うことができます。しかし、延命処置の有無を決める際、多くの場合患者さんの意識がないため、ご本人を抜きにした主治医、看護師、ご家族の3人での話し合いとなります。この場合だと、ご家族が「説得された」と感じてしまうパターンが多く見受けられます。
竹川理事長本来は急性期病院で治療をする際の一番初めに、チューブを入れるか、入れないかを決めてほしいのですが、なかなか難しいのが現状です。まだ回復する可能性はゼロではないため、延命措置の方に傾きがちです。そうしてチューブを入れ、意思疎通ができない患者さんが入院されてくる度に、「果たしてこれは患者さんの尊厳を重んじることができているのだろうか」という疑問が湧いてきてしまいます。
北村先生学会では、「1ヶ月あたりを目処に、自分でご飯を食べられず、意識が戻らなければもう延命処置はやめてよい」というガイドラインがあります。しかし、これはあくまで提案ですので、それに従わないケースが多いです。実際の現場では、3ヶ月も4ヶ月も経管栄養を続けている様子を見かけます。
竹川理事長キリスト教を信仰する国では、自分で食事を摂れなくなったら、あとは天に召されるのを自然に待つという文化があるそうです。海外の様々な病院を見てきましたが、経管栄養や胃ろうを行っている患者さんは見かけなかったですね。
北村先生私もそのように伺ったことがあります。ですから、日本のグループホームで疑問を感じる瞬間があります。食が進まないご利用者に対して「ちょっとでも食べようね」と食事介助を30分間も続けていたりするのです。今だったら小学校の給食でも、時間をかけて無理して食べさせる行為は虐待になりますよね。
竹川理事長そのような観点からすると、健育会グループでも、食事介助に時間をかけすぎている事例があるかもしれません。
北村先生適切なところでやめても良いと思います。10分ほどで介助を打ち切って、それで痩せ細って弱ってしまうのならば、それはその方の命の運命が来ているという考え方を、もっと押し出していくべきです。
竹川理事長これから介助していく人手も減っていくわけですからね。どうやって仕事を効率化させていくかという段階で、患者さんやご利用者の自然な生命活動の導き方について考えていかないといけないですね。