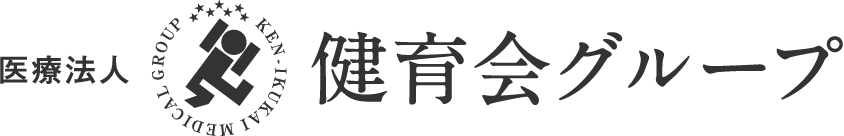竹川理事長意識があるうちは、延命措置を望む方が多いのではないでしょうか。
北村先生実はそうでもなく、「延命措置をしないでほしい」ということを50代、60代のうちから書いておき、70代になってその事前指示書を提出する、という方もいらっしゃいます。現在、日本尊厳死協会には、そうした事前指示書を作成した会員様が7万人いらっしゃいます。
竹川理事長何かフォーマットが用意されているのですか。
北村先生はい。延命措置を望むか望まないかの記載や、「痛みは取り除いてほしい」といった要望、さらには「最期を迎えるとき、愛犬を側に呼んできてほしい」など、ご自身の希望がいくらでも記載できるフォーマットがあります。しかし、その中でも最も重要となるのは「延命措置の有無」の部分です。
竹川理事長意識があるうちに事前に延命措置の有無を提示してくれていれば良いのですが、問題はやはり、すでに意識がない患者さんの場合ですね。院内で患者さんが延命措置で苦しんでいる時、ご本人が穏やかに人生を全うされるためにはどう接するべきか、という考えを健育会グループ全体で共有していなくてはならないと思っています。そのためにも、患者さんが最も安らぎを感じたまま最期を迎えることができる治療法についてご家族と共に考える委員会を立ち上げる必要があると感じています。

北村先生患者さんを平穏な旅立ちへと導いていく取り組みは、少なくとも刑事訴訟にはなりません。一方で、ご家族から「他にも方法があったのではないか」と、後に民事的な訴訟をされてしまう病院もあります。そのようなケースを防ぐためには、日頃からご家族と良好な関係を築き、ご家族の「延命措置は望まない」という意思表示を音声や映像で記録して、「しっかり話し合いをしましたよね」と主張できる、委員会を守るような仕組みを作っておくと良いでしょう。
竹川理事長音声や映像を残しておくのは非常に良いアイデアですね。
北村先生ただ、音声や映像の記録に残していたとしても、実際に患者さんが苦しみを感じている段階で「ご本人も苦しそうだから、鼻から入っているチューブを取るかどうか決めましょう」とご家族に話をすると、「先生におまかせします」とおっしゃる方もいます。
竹川理事長ご家族は判断ができないため、医師に決定権を投げてくることはよくありますね。
北村先生今は、ご本人の意向に沿った治療をすることが浸透してきていますので、最終的な判断はご家族で行っていただかなくてはなりません。しかし、ここに難しさがあります。例えば、延命措置について面談したのが長男の方で、しっかりと話し合いを設けた上で「延命措置は行わない」とご判断いただき、その意向を聞き入れたところ、しばらくして患者さんの長女や次男が現れて、「自分はそのような話は聞いていない」「自分だったらそのような措置に同意するサインなどしない」と、ものすごい剣幕で迫ってくるケースもあります。