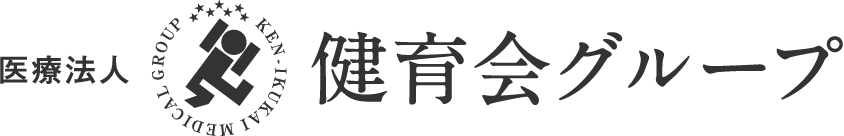前半の各発表・質疑応答を終え、座長の叶谷由佳教授(横浜市立大学院 医学研究科看護学専攻長 老年看護学教授)から、各演題についてのご感想や改善点について、丁寧な講評をお話しいただきました。

1演題目-言葉による抑制は、日々のケアの中で無意識に行われることが多い難しい課題です。今回は研究の中でしっかり問題を見える化できていて良かったと思いました。
対象者を医療従事者全員に広げた部分はとても良いので、今後は各職種の違いや傾向を、さらに細かく分析してもらいたいです。また、経験年数の長い人ほどスピーチロックをしていないといった「結果」に対し、どのような「背景」があってアウトカムに繋がったのかという「考察」をしっかり組み込んでいただきたいです。
2演題目-BPSD症状に対する研究報告がない中、文献レビューや実体検証を実施していた姿勢は良かったと思います。実態調査した「結果」に対し、なぜBPSD症状に対してケアバンドルが重要なのか、といった「考察」をより丁寧にするとさらに良かったと思います。
せん妄に関するケアバンドルと、今回取り上げたBPSDによるケアバンドルの違いを、明確化させるとオリジナリティ溢れたわかりやすい研究になると感じました。
3演題目-文献レビューもしっかり実施され、実際に患者さんに使えるか検証し、共通の指標を編み出していたので素晴らしいと思いました。健育会グループ全体で明日からでも活用できる研究が行えていたと思います。主介護者へ理解されるまでに、どの程度の時間を要したのか明記すると、より実現可能になると思います。
4演題目-以前より、介入研究を行う上で最も大切なことは「介入」の部分だとお話しています。今回は、過去の研究結果を根拠に「勉強会を行う」という介入方法にしたのだと思いますが、そこに至るまでの背景がわかりませんでした。研究を行う上で、なぜこの研究方法に至ったのか、しっかり開示するよう心がけてください。過去に取ったデシベルデータを有意義に使い、現場の改善に繋げてくだいさい。
5演題目-腰痛予防にフォーカスを当て、取り入れやすさを重視したのだと解釈しましたが、なぜ「これだけ体操」を用いたのかという理由や改善効果が表現されていませんでした。「これだけ体操を」介入したことにより、どれほど筋肉の柔軟性が図れるのか、といった根拠を論理的に述べたほうが「結果」の理解度に繋がるように思います。
今回は腰痛のない方に向けた予防策を取り入れていましたが、腰痛のある方に対しての対策はありませんでした。今後の研究では、腰痛がある方に関しても、個別的なアプローチを行って研究の価値を高めてください。
6演題目-有意差がなかったという「結果」を深く「考察」していた点は良かったように感じます。しかし、有意差がないからといって、全ての家族が、不安感を微塵も拭えなかったわけではないはずです。有意差がないという「結果」に至るまでの動きを細分化し、それぞれの効果を明確化させると、より良い発表になったと思います。
7演題目-とてもユニークなテーマだと思いました。小病院2次救急での就労を継続してもらうために、現場の意識を把握したい、という背景から調査をはじめたところ、予想外にもポジティブな意見が多いという「結果」が可視化されていました。ポジティブな意識をより増やしていくための対策案まで深堀りできていればさらに良いと感じました。
8演題目-調査の範囲が、北海道全体だったので、今後はぜひ全国規模の範囲設定をしてもらいたいです。実態調査に関しては「回答率が低いため結果が偏っているのではないか」という意見が質疑応答で出ました。こういった場合は、類似した調査を参考にしたり、介護老人保健施設の調査を見て、信憑性のあるデータだということを「考察」で述べるようにしましょう。