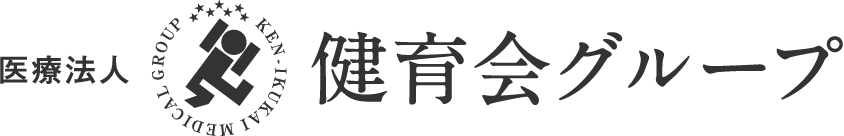「結果」に対する意識が疎かになっている発表も見られました。研究発表は「結果」が全てです。皆さんは「背景」と「考察」がとても長い傾向に見られます。「結果」を何よりも丁寧に説明してください。
また、「結果」と「考察」が結びついていないケースも見られました。
「結果」から見えてきたことを「考察」しなければ、研究をしてきた意味がありません。
「結果」と「考察」が結びついていない発表は、質疑応答で多く意見を求められていました。
例えば「介護老人保健施設における感染対策実態調査 〜COVID-19 5類移行後の課題〜」とう演題目では「回答率が低いのではないか」という質疑応答がありました。叶谷先生もおっしゃっていたように、本来ならこの部分は「考察」で触れていなければいけません。聞いている側に疑問を持たせないことが発表には求められます。
回答率が低いという問題は、バイアスを取れば解決します。全体の母数に対して、回答した人の結果が偏っていない、ということを検証できていれば、きちんと統計の採れたデータとして胸を張って開示できるようになります。
どれだけ調査を依頼しても、返ってくるのは全体の20%ほどです。「回答率の低さ」をマイナスに捉えそのままにするのではなく、バイアスを取ることに力を入れましょう。
次に、比較対象の問題についてお話します。比較対象にも様々な種類があります。
今回ですと、腰痛がある分と、腰痛がない分、との比較だったり、勉強会をやる前、と勉強会をやった後の比較など、多種多様でした。今回の発表会では、きちんと比較対象を行えていたように思います。
統計解析については、これまでに増して様々な手法で行われており、有意性の比較もきちんとできていました。
しかし、有意の差がないという結果が出た場合の対処法に誤りがありました。
有意の差がないから同一である、という見解は間違っています。「差がない=同一」ではありません。正しくは「差が検出できなかった」ということになります。症例数を増やしたら差が出るかもしれない状態なのです。
症例数が少ない状態で有意差を認められなかった場合は「差が検出できなかった」という扱いをしてください。
健育会グループの発表会は、組織間でプロセスを共有したり、効率化することを目指す「内的な一貫性」での行いです。発表をするにあたって、リハーサルも行うでしょう。その際は必ず建設的なことを発言しましょう。
仲間の話を聞いてどこを直すべきか、積極的に指摘をしてください。あら探しをしたり、アドバイスをしないという行動は、チームとして褒められるものではありません。
言うべきときにしっかりと言う文化が健育会グループにはありますので、その伝統を大事にしてください。
今回の発表では大変いいディスカッションができていたと思います。現実的で、オーディエンス側がより良い参考例をスライドに映して皆さんに伝える、といった行動もとても印象的でした。