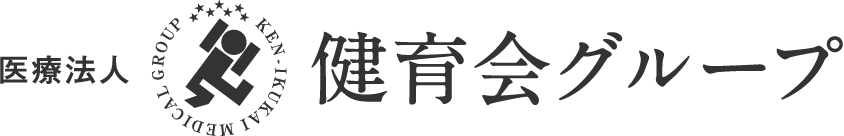続いて、長谷川友紀教授(東邦大学 医学部社会医学講座 医療政策・経営科学分野 教授)より、全体の総評をいただきました。

今日は、一日楽しませていただきました。看護師は熱い思いを語り、一方でセラピストは冷静で数値化した分析をしており、職種によって見える視点が異なるように感じました。
皆さんとても頑張っており、毎年レベルが上がっているように思います。
しかし研究に熱心になるあまり「Our Team」の意識が薄れてしまっているように感じました。この研究会は「Our Team」という考えのもと存在しています。ただ研究をして違いを見出すだけでは「Our Team」の活動としては不十分です。
自分たちが取り組む研究が、どうすれば健育会グループ全体の質の向上につながるか、という視点で臨むと、さらなる飛躍が見込めるはずです。
皆さんが次のステージへ進む上で、どのようなことが課題になっていくか、例を上げながら詳細をお話をさせていただきます。
スピーチ力に関しては、とても上達したように感じました。過去には、俯いて小声で呟いたり、ただ資料を読み上げている方も多く見られました。このような態度では、いくら言葉を発しても、オーディエンスに響いていきません。声のトーンを低くし、ゆっくり話す。そして語尾はハッキリと発音する。これが発表をするうえでの原則です。今回は基本をしっかりと押さえて発表することができていたように感じます。
パワーポイントに関しては、改善する部分が多いように見受けられました。
まずは、スライドの中の文章についてです。あまりにも文字が多いため、読み取ることが困難でした。
パワーポイントの字は、できるだけ少なく、表記は箇条書きにしましょう。箇条書きで記されたことをスピーチで補い、詳細を伝えるようにしてください。
文字のポイント数は、14ポイント以下は使わないほうが賢明です。細かい字は見えづらくなってしまいます。
また、結果を報告するうえで一覧表を示す場合は、強調したい箇所に線をつけるなどして、見てほしい部分と発表内容をリンクさせましょう。最も重要な箇所に目がいくよう心がけてください。
次に、全体の構成についてお話します。それぞれの思いが強いあまり、研究に至るまでの「背景」の説明がとても長くなっていました。「背景」に関しては、スライドを1、2枚に抑えるようにしましょう。そして「背景」よりも方法に重きを置きましょう。どのような方法で、何を測ったのか。この部分が有耶無耶で、開示されていない発表もいくつかありました。