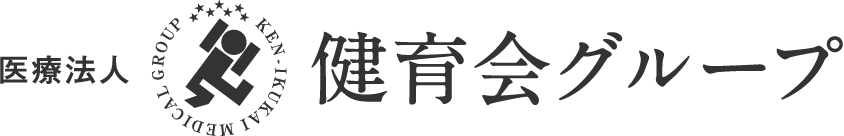はじめにも触れましたが、皆さんが次のステップに進むために必要なことは「Our Team」をより意識することです。自分たちの研究が、健育会グループにとってどのような貢献につながっていくのかを、研究する上でしっかりと念頭に置いてください。
「医療従事者がスピーチロックと認識する要因の実態調査」では、言葉による抑制を防ぐために勉強会をやる流れとなり、どういった言葉が危険なのか話し合うことで、感受性が高まった、と発表していました。
しかし、ただ感受性が高まるだけではいけません。使用してはならない言葉を使わないための具体的な対策についてまで考えてください。
例えば「NGの言葉一覧を作る」ことや「普段から正しい言葉が出てくるようなしくみを作る」といった勉強会の実施が求められます。研究発表で聞き手側が知りたいのは、こういった勉強会の内容です。
どれくらいの時間がかかり、どのような人が講師で、どのような教材を使ったのか、という具体的な対策内容を知りたいのです。発表時にここまで行えていれば「結果」を標準化することができ、グループ全員で研究内容をすぐに現場に取り入れることができます。
「手すりの種類の違いが立ち上がり動作時の下肢筋活動に及ぼす影響」では、筋力訓練において「Pull」と「Push」どちらがより望ましいのかといった質問や、患者さんによってどちらの動作訓練を行えば良いのか、という疑問が挙げられました。
様々な視点の疑問に応えられるような検証をあらかじめしておけば、どの病院、施設でもいち早く課題解決に向けて実践をする事が可能になります。この姿勢を意識すればそれぞれの研究が「Our Team」としてさらなる躍進を遂げると思います。今回の課題をしっかりと受け止め、「Our Team」としてより素晴らしい活躍をなさることを期待しています。
最後に、私から理事長講評として以下のような内容を皆さんに話しました。