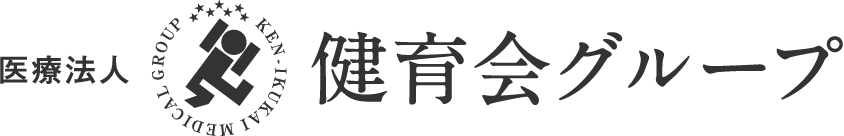審査結果発表の後、審査委員長を務めた長谷川先生から、全体の講評をいただきました。

昨年、一昨年は「経費削減」や「幸せホルモン」という特定のテーマを設定していましたが、今回は自由にテーマを選んでもらいました。そのため、テーマ選定に難しさを感じた方もいたのではないでしょうか。皆さんそれぞれ多岐にわたる活動をされており、大変興味深く拝聴いたしました。
TQM活動を進める上で重要だと考えられるポイントは二つあります。一つは、その活動がオーソドックスなTQMの手法に則っているかという点です。
そしてもう一つは、その取り組みが業務の中にどのように展開し、どのような波及効果を生むか、という点です。
これら二つの視点から皆さんのTQM活動を総合的に評価しています。チームのため、そして健育会グループとしてより良い医療を提供するために、どのような貢献ができるか、といった部分が非常に大切になります。
例えば、コスト削減だけでなく、満足度の向上やミスの減少といった効果があれば、その活動はより価値のあるものとなります。そのノウハウが他の病院でも応用可能であるかどうかも大きなポイントです。
皆さんは様々な課題を掲げ、目標を設定していました。目標設定には、いくつか重要なポイントがあります。
まず、目標は目に見えるものであることが求められます。そして、その目標を行動という形にできている、ということも重要です。
単に「自信がある」「品質が良い」といった曖昧な表現は目標設定とは言えません。例えば、「各職種の専門性を活かした在宅復帰支援をめざして~LSねりまとしてのチームアプローチの振り返りと体制見直し~」を例に挙げますと、「在宅支援の知識について自信がある」というような表現では不十分です。「在宅支援サービスの開始が遅れる」という課題を目的に設定していれば、その問題を解決するための行動が生まれ、問題がいつ解消されたかが測定できるようになります。
行動に移せるか、そして測定できるかという点が非常に大切です。
また、課題の範囲設定も重要です。「人材育成 BLS実践研修」ではBLSの実践を促す取り組みを行っていましたが、BLS研修はケアに関わる全ての職員が受けるべきごく当たり前な内容です。このような課題を設定するのではなく、健育会グループのスタッフとして、さらに意識を高く持ち、もう一歩先の目標を設定することが望ましいと思います。
「しおさい長期ご利用者における水分摂取量の増加~活力ある生活を送る為のプロジェクト~」は、わずか3人を対象としており、TQM活動としてはインパクトが弱いと感じられました。施設全体の職員の水分摂取目標を設定し、問題意識を共有した上でアプローチすれば、説得力が格段に増すように感じました。
特性要因分析についても気になった点がありました。「なぜ何々ができないのか」という要因ではなく、「何々ができない」「何々が遅れる」といった具体的な特性を捉えることが重要です。要因が対策とずれている発表がいくつか見受けられました。論理的な整合性に注意をしてください。